1. はじめに
「マイクラって子どもに悪影響があるのでは?」
そう思って心配する親御さんは多いと思います。
我が家でも、子どもが5歳のときにマイクラを始めた当初は「まだ早いかな?」と不安がありました。
しかし、そこから9歳になるまでの5年間、親子で一緒にマイクラをプレイしてきた結果、その印象は大きく変わりました。
この5年間で感じたのは、マイクラは単なるゲームではなく、遊びながら「考える力」を育てる最高の教材だということ。
実際に一緒に遊ぶ中で、想像力・計画性・プログラミング的思考など、子どもの成長につながる力が自然に伸びていくのを感じました。
この記事では、マイクラを5歳から9歳までプレイしてきた実体験をもとに、
「マイクラは子供に悪影響があるのか?」
「良い影響はどんなものがあるのか?」
を、実体験をもとにわかりやすく解説します。
教育効果の全体像(4つの力の整理と家庭での活かし方)は、次の記事でまとめています。
→ マイクラの教育効果は本当?知育・考える力を伸ばす遊び方と注意点
そもそもマイクラがどんなゲームなのかを知りたい方は、マイクラってどんなゲーム?親子向け解説の記事もあわせて読んでみてください。
あわせて、「Switch版とスマホ版のどちらで遊ばせるか」で迷っている方は、機種ごとの違いをまとめたマイクラはSwitch版とスマホ版どっちで始める?親目線でメリット・デメリットを徹底比較!も参考になると思います。
マイクラが好きな今は、「ゲームが好き」を少しだけ“学び”に寄せやすいタイミングです。
まずは無料で試して相性チェックできる教材をまとめたので、よければ先に見てみてください。
2. マイクラは子どもに悪影響がある?最初に感じた不安
マイクラを始める前は、「ゲーム依存にならないか」「視力や睡眠への影響は大丈夫?」と心配していました。
また、ゲームの世界に夢中になって現実との区別がつかなくなるのでは、という不安もありました。
そこで我が家では, 最初から次のようなルールを決めました。
ポイント
マイクラを安心して遊ぶために、最初に決めた我が家の基本ルールです。
- 平日は1時間、休日は3時間まで
- ゲームスマホは21:30まで
- ゲームは宿題や習い事の練習が終わってから
- プレイ中は親が近くで見守る
このルールを守ることで、悪影響はほとんど感じませんでした。
むしろ、ルールを自分から守る習慣や、時間を意識して行動する力が身についています。
3. マイクラを5歳から始めて感じた“良い影響”
マイクラは遊びながら、想像力・計画性・考える力など、子どもの成長につながる力を自然に伸ばせるゲームだと感じています。
特にどんな力が育ったのかは、実体験を整理したマイクラで伸びた3つの力の記事でも詳しく紹介しています。
3-1. 想像力と創造力が育つ
マイクラでは、ブロックを自由に組み合わせて建物や街など、なんでも作ることができます。
粘土やレゴブロックでも同じようにイメージしたものを形にすることができますが、
色や数に制限があり、どうしても思うように形にできず、中途半端な形になってしまったという経験をした親御さんも多いのではないでしょうか。
マイクラは、ブロックの色や形が豊富で、数についてはなんと無限なので、思いついたアイデアをすぐに形にできるのが魅力です。
思いついたものがすぐ形にできるので、「次はこれを作る!」「次はあれを作る!」と、
自分の中に浮かんだイメージを次から次へと作っていくようになり、
想像力と創造力の両方がどんどん伸びていきました。
(わたしは子供が次々にイメージを形にしていくのを見ていて、「今日も芸術が爆発しているな」と感じていました。)
ブロック遊びが好きなお子さんにはハマると思います。
3-2. プログラミング的思考・計画性が身につく
マイクラの中でもサバイバルモードは、「やりたいこと」に対して「必要な工程」を逆算して考える力を育ててくれます。
たとえば、
牛の牧場を作りたい!
↓
牛を増やすには小麦が必要!
↓
小麦畑を作るには水が必要!
↓
水を汲むためにバケツが必要!
↓
バケツを作るには鉄が必要!
というように、目的から逆算して行動するようになります。
はじめはその都度必要なものを集めるだけでしたが、だんだんと「先を読んで計画的に行動する」ようになりました。
補足
サバイバルモードは5歳くらいだとまだ難易度が高めです。敵(モンスター)が出たり、食料を確保したりと、やることが多くなるため、最初はうまく楽しめない子もいます。
我が家の場合も、サバイバルをしっかり楽しめるようになったのは小学3年生ごろ(難易度イージー・親サポートあり)からでした。個人差はありますが、2〜3年生くらいでチャレンジしてみるのがおすすめです。小さいうちはまずクリエイティブモードで自由に作る楽しさを味わい、少しずつサバイバルへ移行すると自然にステップアップできます。
また、「夜になったら寝る」「敵が出たら逃げる」といった条件による行動の切り替え(if的思考)も自然と身につきます。
装置がうまく動かないときも「どこが違うんだろう?」と試行錯誤しながら修正するようになり、これは正にプログラミングの「デバッグ」作業です。
さらに最近では、「ドアを自動で開くようにしたい」「素材集めを効率化したい」など、仕組みづくりや自動化の発想も出てきています。これらはまさに、遊びの中で育つプログラミング的思考そのものです。
※このあたりの「何歳からマイクラを始めると良いか」については、実体験をもとにした別記事「【実体験】マイクラは子どもに何歳から?」で詳しくまとめています。
3-3. コミュニケーション力・協調性が育つ
親子でマルチプレイをしていると、また友達とプレイをする時も、「何を目標にするか」「次に何をやるか」「誰がどの役割を担当するか」を話し合う機会が自然と増えます。
この“考えて協力して達成する”というプロセスは、やらなければいけない事やルートが定められていない、何をやるのも自由なマイクラならではです。
息子には、できるだけ自分で考えてもらい、私は必要なときにアドバイスをする程度。
そのおかげで、協調性・リーダーシップ・コミュニケーション力など、チーム活動で必要な力が自然に身についています。
3-4. 調べる力・理解する力がつく
最近では、わからないことを自分でネットで調べて解決するようになりました。
「クロック回路ってどう作るの?」「隠し扉を作る方法は?」など、調べながら自分で試しています。
ただ情報を読むだけでなく、“説明を正しく理解して正しく実行する力”がついてきていて、これは勉強にも実生活にもつながる大切なスキルだと感じます。
4. 悪影響や注意点もゼロではない
まず前提として、マイクラのゲーム内容そのものについては、他のアクションゲームやガチャ中心のスマホゲームと比べると、暴力表現やギャンブル的な要素はかなり少ないと感じています。
血が出たり、リアルな攻撃シーンがあったりするわけではなく、標準のマイクラにはランダムで当たりを狙うようなガチャ課金もありません。
そのうえで、やはりルールを決めずに自由にプレイさせてしまうと、長時間になりがちです。
我が家では次のルールを守っています。
ポイント
マイクラだからと油断せず、「時間」と「生活リズム」のルールを先に決めておくことが大切です。
- 平日1時間、休日3時間まで
- ゲームスマホは21:30まで
- やることを終えてからゲームOK
- 約束を守れないときは一度休憩
このように明確なルールを作っておけば、生活リズムが乱れることもなく、安心して楽しめます。
感情的になったり、現実とゲームを混同したりするような悪影響は今のところありません。
ゲーム時間や約束の決め方については、別記事のマイクラのやりすぎ防止と時間ルールの決め方でも詳しく解説しています。
また、オンラインプレイ時のフレンド機能やチャットの安全面が心配な場合は、Switch版マイクラの具体的な設定方法をまとめた「マイクラのフレンド機能は子どもに危険?Switch版で親がやっておきたいオンライン安全設定ガイド」もチェックしてみてください。
5. 親が工夫したこと・意識していること
5-1. プレイルールの設定
「やることをやってからゲーム」「平日1時間・休日3時間」など、ルールを最初に決めて共有。
子ども自身がそのルールを守るように意識することで、自己管理力も育ちます。
我が家の場合は、21:30の終了時間までに如何にその日のゲーム時間を使い切れるようにするか、逆算して計画的に行動できるようになっています。
マイクラ全体のルール作りやトラブル防止の考え方は、別記事の親子でマイクラを遊ぶときのルール作りとトラブル防止のコツにもまとめています。
5-2. 子どもに考えさせる進め方
基本的には子ども主導でプレイ。
親は「どうしたらうまくいくかな?」と質問して、子どもが自分で考えるように促すスタイルにしています。
5-3. 褒め方・関わり方
すごい建築や工夫ができたときは素直に「すごいね!」と伝える。
結果よりも「工夫した過程」を褒めることで、モチベーションが長く続くと感じます。
6. マイクラを通して感じた「考える力」の育ち方まとめ
マイクラは、ただのゲームではありません。
遊びながら自然に想像力・計画性・プログラミング的思考・協調性が育つツールです。
親が関わり方とルールを工夫すれば、悪影響よりもずっと多くの良い影響を感じられます。
7. まとめ|マイクラは“親子で学べる最高の遊び”
- 想像力・計画性・考える力を育てる
- 親子共通の話題が増えて関係が深まる
- 飽きにくく、長く楽しめるコスパの高いゲーム
「マイクラは悪影響では?」と心配している方も、
まずは一緒に遊んでみてください。
きっと、子どもの成長や考える力の芽に気づけるはずです。
8. 関連記事
「ゲームが好き」を、少しでも“学び”につなげたいと感じたら、まずは次の2記事から読んでみてください。
→ まず無料で相性チェック|無料で始められる子ども向けプログラミング教材・体験まとめ
→ 我が家がデジタネを選んだ理由|無料体験→比較で決めた本音レビュー
👉 マイクラの教育効果は本当?知育・考える力を伸ばす遊び方と注意点
👉 Switchとスマホでマルチプレイする方法(親子プレイに最適!)
👉 マイクラはSwitch版とスマホ版どっちで始める?親目線でメリット・デメリットを徹底比較!
👉 親子でマイクラを遊ぶときのルール作りとトラブル防止のコツ
📕親子でマイクラを始めようシリーズ
「マイクラを始めてみたいけど、何から覚えればいい?」
そんな親子のために、遊び方・設定・機種選びなどの基本をわかりやすくまとめました。
どの記事から読んでもOKです。気になるテーマからチェックしてみてください。
-

マイクラはSwitchとスマホどっちがいい?一番の違いは料金(NSO)|親目線で比較
-



【実体験】マイクラは子どもに何歳から?始める目安と年齢別の遊び方
-


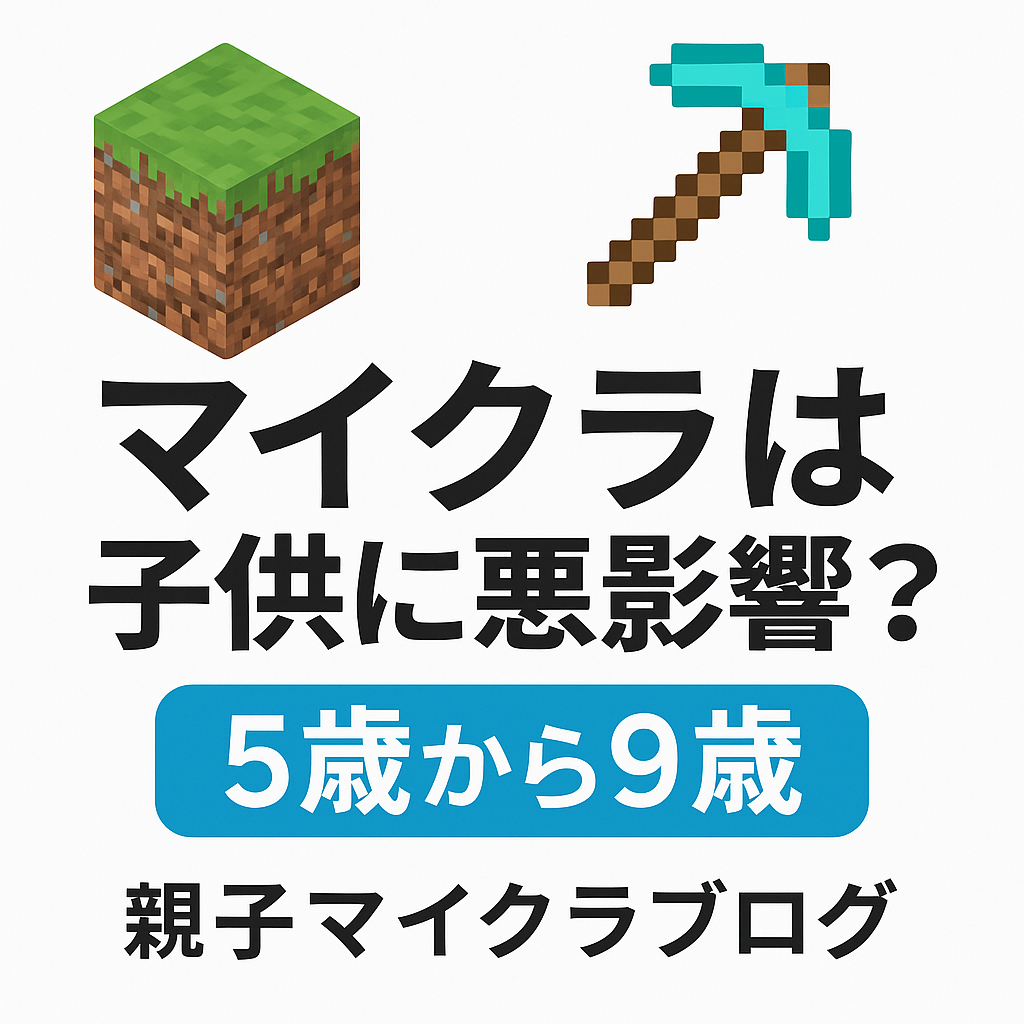
マイクラは子どもに悪影響?5年間の実体験でわかった意外な効果
-



マイクラをスマホとSwitchで一緒に遊ぶ方法【検証済み】|つながらない原因と対処
-



【徹底比較】マイクラ統合版とJava版の選び方
-



マイクラ難易度のおすすめは?違いと選び方|初心者・子ども向け
-



マイクラのモード種類を完全解説!
-



【初心者向け】マイクラの始め方|Switch・スマホでの始め方を解説
-


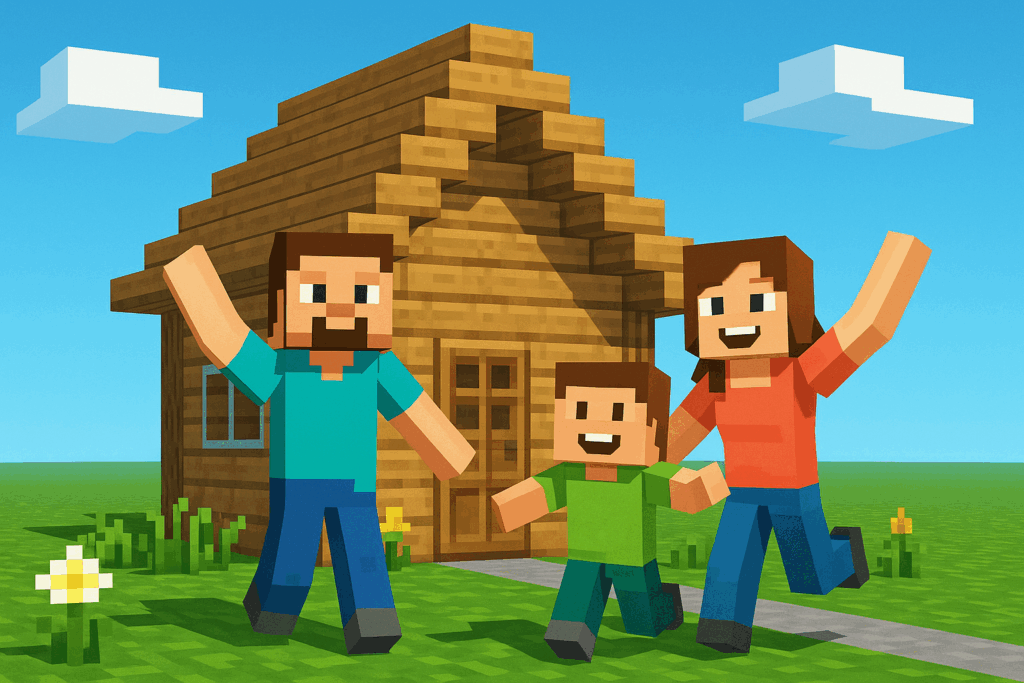
マイクラってどんなゲーム?親子向け解説
